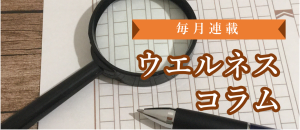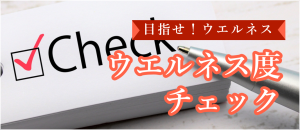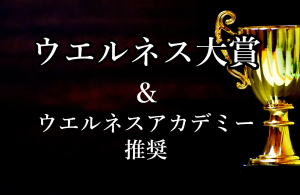アルコールの正体

アルコールの正体
ウエルネスアカデミー評議員 紙谷名枝子
2016/8/1
「酒は百薬の長」とは中国王朝の一つ前漢の歴史書「漢書」の「食貨志第四下」に出てくる 言葉です。
その後吉田兼好は徒然草の中で「 酒は百薬の長といへども、満(よろず)の病は酒よりこそ起(おこ)れ」といっています。
そのころからお酒は飲み過ぎるといろいろな病気になることが知られていました。 またアルコールは覚せい剤やヘロイン、大麻などの薬物と同じ依存性(使っているうちに同じ酔いを得るためには量が増え、自分ではコントロールできなくなる)のある薬物なのです。
さらに私たち日本人は、アルコールを分解する肝臓にある酵素2つを遺伝子上に全く持っていないか、1つしか持たない人が45%ほどいる民族なのです。
つまりアルコールに弱い人が半分近くいることになり、ご自身の家族の中に、アルコールに弱い方々がいたり、消毒用のアルコールで皮膚が赤くなるとか、お酒を飲むと気分が悪くなるなどの症状の出る方は、アルコールを分解する酵素を持っていない可能性があります。
また肝臓での分解スピードも、1時間で体重1kg当たり0.1g程度(体重50kgの方で5g)というゆっくりなため、残りのアルコールは、血中に入ったまま全身を回ることになり病気につながるのです。
さらにお酒は、文化や習慣と深く結びついていて人間関係が優先するために、間違った知識が広がっている薬物でもありますます。
例えば、練習すれば強くなるとか、アルコール依存症者は意志が弱いからやめられないとか、高血圧はアルコールを飲むと下がる、飲酒の後コーヒーや水を飲んだり、汗をかけば、尿をたくさん出せば、吐けば早く抜ける、ウコンやオルニチンを飲めば早く抜ける、睡眠薬より安全、という誤解や思い込みが多いのですが、基本アルコールは酵素による分解のみで、二酸化炭素と水になるまで抜けないのです。
またアルコールは、血液に入って全身を回りますから、血管、心臓、脳(認知症、脳卒中、脳萎縮)、神経系、消化器(胃、腸、すい臓、肝臓等)、骨、生殖器、さらに糖尿病、ガン、高血圧、痛風、栄養障害等々ありとあらゆる病気を起こしますし、女性は男性より依存症になりやすいこともあります。
さらに酔って理性がマヒし言葉や態度で相手を傷つけてしまうなど、コミュニケーションがうまくできずに、家族や友人等との人間関係を危うくする危険も無視できません。その中でもイッキ飲みや飲酒運転、アルコール依存症は大きな社会問題にもなっています。
それではどのくらいのお酒=アルコール量が健康的な飲み方なのでしょうか? 1日1単位の飲酒・・4時間で分解できるアルコール量は25gほど(ビンや缶に%で表示)、この量が健康的です。
1週間7単位・・「1日1単位以上飲んだ時は休肝日を設ける」とされています。
*酵素を2つともまたは1つだけしか持たない方々は、お酒を飲むことは大変危険です。
こうしたアルコールの正しい知識をもって、楽しく健康的な飲酒を心がけ、自分らしい健康な生活を手に入れましょう。
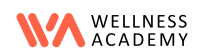 一般財団法人ウエルネスアカデミー
一般財団法人ウエルネスアカデミー